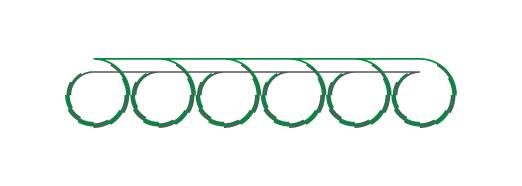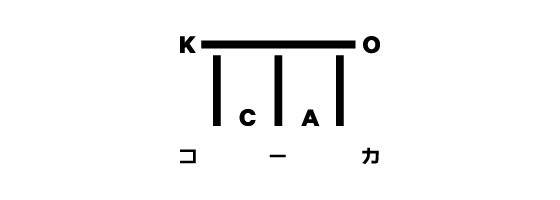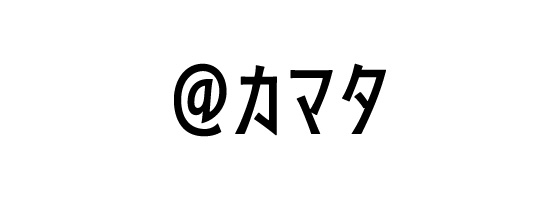工場紹介③:ものづくりコミュニティの再生へ ——株式会社テクノロジーリンク
REPORT

テクノロジーリンク代表取締役の黒尾守さん
ブローカーのおじさんたち
かつて大田区のものづくりの現場には「自転車カゴに図面を入れて街を一周するとモノが出来上がる」という話があった。
実態は、さまざまな職種の町工場を回る「ブローカー」と呼ばれたおじさんたちがいて、その人たちが活躍していたということらしい。
彼らは、図面から正確に要求を読み解き、実現のためには何が必要で、具体的にどこの町工場に頼めばいいかを瞬時に判断できる人たちだった。
当時はメールもファックスもない時代で、町工場の職人たちはそれぞれの現場から離れられなかった。
その間を彼らが動き回ることで、さまざまな要素技術をもつ大田区のものづくりはネットワークされていたのだ。
しかし近年になると、クライアント側の発注形態にもより透明性が求められるようになり、ブローカーのおじさんたちは次第に姿を消していったという。
モノを作らないものづくり
クライアントと町工場をつなぐ媒介者がいなくなってしまったことによる弊害は、やはり小さくないようだ。
株式会社テクノロジーリンク代表取締役の黒尾守さんは、「表面的な価格競争の世界になり、技術的なミスマッチも多い」と指摘する。
テクノロジーリンクでは「モノを作らないものづくり」をコンセプトに掲げ、そうしたミスマッチを解消するためのマネジメントに力を入れてきた。
最近では、医療機器の製造販売や、環境プラントからロボットの部品に至るまで、多岐にわたる受託製作も行っている。
黒尾さん自身も、蒲田生まれの生粋の町工場育ちだ。
家業も試作や開発を主とする町工場だったため、若い頃からいろいろな材料や機械に触れる機会も多かったという。
家業を手伝いながら独学で経験を積み、徐々に紹介や口コミで仕事を受けるようになり独立。
2010年に株式会社テクノロジーリンクを開業した。
起業から梅森プラットフォームへ
テクノロジーリンクを起業した頃は、工場を持たない完全ファブレスを考えていたそうだが、次第に試作のための最低限の施設は欲しいと考えるようになっていったという。
「モノを作らないものづくり」とはいえ、微調整や仮組みが求められる局面はある。
ちょっとだけ削りたい、一カ所だけ小さな穴を開けたい、といった状況にすぐに対応するためにもある程度の設備は必要で、それによって仕事の能率は向上し、できる仕事の幅も広がる。
最近では水に関わる装置を扱う案件も多くなったため地上階の物件を探していたところ、梅森プラットフォームに辿り着いて、入居を決めた。新しい場所で、必要な機材を揃え、ものづくりのための拠点が整った。
新しいものづくりのコミュニティを
梅森プラットフォームでは、すでに町工場とデザイナー・クリエイターたちのコラボレーションが実現している。
そこへの入居にあたり、KOCAが有するデジタル工房や、デザイナーやクリエイターたちとの協働についても期待をしているという。
「昔は醤油の貸し借りのように近所の工場同士で気軽に技術や知恵を補いながら助け合ったものでした。
梅森プラットフォームも見ようによっては高架下にある長屋の町工場群なので、気軽に貸し借りができるような近所づきあいができたらいいなと思っています。
デザイナーさんたちからも、製品の仕上がりについていろいろアドバイスをもらえると嬉しいです」と、黒尾さんは語る。
梅森プラットフォーム内での交流から、それこそ大森町駅から梅屋敷駅へと移動する間にモノができあがるような、新しいものづくりのコミュニティが生まれてゆくかもしれない。
(文・和田隆介)